2024年度アニュアルレポートから抜粋
私たちは 2025年も BRA駆動開発を軸にして、教育事業(人材育成)と研究開発促進事業の二本立てで活動を進めます。
教育事業(人材育成事業)
今年度の教育は、LLM を活用した BRA 駆動開発の自動化 が加速している現状を踏まえ、「LLM と人間の協働スキル」を重点に据えます。従来の「手作業で BRA データを作成できる人材」だけでなく、以下のような能力を育成します。
- LLM による仕様草案の生成とブラッシュアップ ─ 適切なプロンプト設計と結果の批判的評価
- 人間↔LLM 相互レビュー ─ 専門家が LLM 出力を検証し、逆に LLM が専門家のドラフトをチェックする二重確認フローの習得
- 自動化パイプラインの監督 ─ BIF/HCD 自動生成ツールの運用・エラー検出・品質保証
*BIF (Brain Information Flow: BIF) 〜解剖学的構造を基盤とした脳情報フロー図
*HCD (Hypothetical Component Diagram) BIFに整合的な計算機能の記述である仮説的コンポーネント図
これらを実践的に学ぶ場として、国際全脳アーキテクチャワークショップ(WBAW)を開催します。まずは11月に国際会議 The International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2025) でワークショップを開催します。またそこでハンズオン形式のレクチャーも行います。
また、WBAI奨励賞は従来は脳型AGIの技術開発において波及効果の高い成果を上げた研究者としていましたが、BRAデータ作成やそこでのLLM活用などの活用事例も評価するように調整することを検討します。
研究開発事業
WBAIの研究開発促進事業は、2027年初頭までにWBRAの初期版完成を目指し、昨年度公開した技術ロードマップ(図参照)に沿って進められています。他方、LLM の能力向上によりBRA 駆動開発の多くが自動化できる段階に入っています。2025年度は「人間が確認するか、人間を LLM が確認するか」という 相互検証型ワークフローを取り入れて推進します。
※以下の説明において”[]”で、ロードマップ上の位置を示します。
表:WBA研究開発カテゴリ一覧
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 説明(新) |
| 方法論 | BRAデータ管理システム | BRAデータ、投稿審査フロー、BRAES、審査ツール等の方法論策定 |
| 方法論 | BRA可視化 | BRAデータ可視化ツールの開発とレイアウト・表示項目の検討 |
| 方法論 | HCD設計 | BRA設計における特にHCD設計のための方法論構築 |
| 方法論 | BRA全般 | BRA駆動開発の方法論に関する研究 |
| 運用 | BRAデータ管理システム | BRAデータ、投稿審査フロー、BRAES、審査ツール等の運用(マニュアル整備・バージョンアップ等を含む) |
| 運用 | BRA可視化 | BRAデータ可視化ツールの運用とレイアウト・表示項目の最適化 |
| 運用 | WholeBIF管理 | WholeBIFへの追加項目の審査と登録(BDBRA含む) |
| 運用 | データアップデート | データのバージョン管理実施 |
| 設計 | BRAデータ管理システム | BRAデータ、投稿審査フロー、BRAES、審査ツール等の設計 |
| 設計 | BIF構築 | BIFの作成と関連作業の実施 |
| 設計 | HCD設計 | HCDの設計と関連作業の実施 |
| 設計 | WholeBIF構築 | 脳全体を統合するBIFデータの構築作業(BDBRA含む) |
| 設計 | WholeHCD構築 | 分散構築されたHCDの統合作業 |
| 評価 | BIF信憑性評価 | BIFの信憑性評価実施 |
| 評価 | HCD評価 | HCDの機能性・構造整合性評価と審査フロー・自動審査の実施 |
| 評価 | 忠実度評価 | 実装の評価(異常系含む)、活動再現性評価、機能評価の実施 |
| 評価 | 異常系評価 | パフォーマンス変動の評価(人間もしくは動物の機能不全) |
| 評価 | 活動再現性評価 | ソフトウェアの振る舞いと実験で得られた神経活動の比較評価 |
| 評価 | 構造忠実度評価 | 実装コードの構造類似性評価 |
| 評価 | 実行環境整備 | 脳型ソフトのタスク実行・テスト環境の整備 |
| 実装 | 実装環境整備 | ソフトウェアプラットフォーム(BriCAなど)の構築 |
| 実装 | アーキテクチャ実装 | HCDを参照したソフトウェアフレームワークへのアーキテクチャ実装(構造忠実度評価可能な形式) |
| 実装 | BRAデータ管理システム | BRAデータ、投稿審査フロー、BRAES、審査ツール等の実装 |
| 実装 | コンポーネント実装 | HCDのCircuit毎プロセス記述を参照したソフトウェアコンポーネント実装(活動再現性評価可能な形式) |
| 実装 | 実装環境整備 | ソフトウェアプラットフォーム(OpenAI Gymなど)の構築 |
| BRA以外 | 新機能の検証 | 未知の計算機構探索のための実装(ヒトを含む動物が解決可能な特定タスク対象) |
| BRA以外 | 新機能の設計 | 未知の計算機構の設計(ヒトを含む動物が解決可能な特定タスク対象) |
| その他 | 人材育成 | 実装プロセス実行可能な技術者を育成するための教育的な実装 |
| その他 | AIアライメント | AIと人類の調和を目指す活動の実施 |
以下ではこれらの活動の中でも、BRA駆動開発において中心的な部分として下図のロードマップに記されている BIF構築と HCD構築について詳しく述べます。
BIF構築の高度自動化
神経科学文献の自動登録システムをWholeBIF(全脳BIF)へ実装し、脳科学文献から得られる知見を効率的に統合します。2025年には WholeBIF を完全自動で構築する目標を掲げています。この目標に向けて私たちは以下のステップでBIF構築活動を進めていきます。
- WholeBIFの自動構築システムの本格運用を開始し、継続的な自動更新の仕組みを導入します[B9]。
- BIFの要素である領野間投射の信憑性評価の技術を確立および適用し、WholeBIF更新システムの運用改善を進めます。こうして信頼性の高いデータベースの構築を目指します[B10]
- 上記を組み合わせて、BIFの大部分を完全自動で最新の脳科学研究の成果をタイムリーに反映できるようにします。
HCD / FRG 構築の半自動化
2027年にWBRAの初期バージョンを実現するには、脳全体においてできるだけ網羅したHCD/FRGの構築が必要になります。それを踏まえて、2025年の HCDとFRG構築においては以下の活動を進める予定です。
- HCDセットの手動アライメントと整理作業を継続し、高次機能として統合された脳機能モデルの構築を進めます [H5]。
- HCDのコンポーネントやFRGのノード間の関係を自動評価する技術を開発します[H6]
- 上記[H6]を利用しながら、HCDとFRGを自動設計する技術を開発します [H7]。
- 上記[H6][H7]の技術は試作やエラー検出が可能なレベルですが、信頼性が不十分なため、専門家の能力を組み合わせて効率的にHCD/FRGを開発します。
実装ガイドラインの整備
WBAIは開発を促進するという立場にあるため、ヒト脳型AGIの本格的な実装は行わないこととしています。しかしながら、ヒト脳型 AGI を他機関が実装・検証しやすくするために、Brain‑morphic Implementation & Testing System(BITS) を計画しています。今年度は以下の骨子を固め、ガイドライン草稿をまとめます。
- 目的:BRA の設計情報を読み込み、仮想環境で動作する Brain‑morphic ソフトウェアを構築・評価できる標準的なフレームワークを用意する。
- 方針:HCD から計算グラフを生成し、モデルは BCM(生物学的拘束あり)または BAM(拘束なし)を選択可能とする。
- 評価:タスクベンチマーク上で機能・活動・構造・性能をチェックし、LLM と専門家による相互レビューで品質を担保する。
- 公開計画:2025 年度内にガイドライン草稿を公開し、JSAI2025 で BITS 構想を発表、得られたフィードバックを反映して改訂する。
これによりBRA 駆動開発の成果を実装面までつなぐ道筋を示します。
人類と調和したAIのある世界へと向かうための活動
序文で説明した 「人と多様な AI の共生インタフェース」を実現するNeuroQuad フレームワーク を中心に以下の学術・社会貢献を進めます。
- 学術研究発表
海馬体モデルを題材に脳型AIにおけるCMD(監視)機能を取り上げ、異常検知のプロトタイプを実演します。また、解釈性の有効性を示し、国際会議や論文を通じてその成果を公開します。 - 社会対話(WBA シンポジウム)
年次シンポジウムでは「ヒト脳型 AGI はヒトと多様な AI の間に“信頼”を築きうるか?」といったテーマに、NeuroQuad フレームワークに関わるパネル討論を行います。
2025年度の予算
予定収入は約46万円で、主に会費収入からなります(2024年度の会費収入は約54万円でした)。当期予定収入と前期繰越金約639万円を合計すると約685万円となります。支出では、管理費に約81万円、謝金、賞金、通信費を含む事業費に約84万円、計約166万円を予定しています(当期予定収入との関係では119万円の赤字になります)。なお、2024年度の予算では管理費に約81万円、事業費に約82万円の計約164万円の支出を予定していました。
おわりに―“信頼のインフラ” をともに築くために
AI は自分自身を急速に賢くできる段階に入りました。人類が安心して AI と共に未来を築くには、まず AI を心から信頼できることが欠かせません。
私たちは、人の脳の構造や動きを手がかりにしたヒト脳型 AGI の開発を進めています。これにより「どう考えたかが分かる」「相手の気持ちをくみ取って応える」「嘘やごまかしを見抜く」といった力を備えた、AI と人を結ぶ信頼の仲立ちが誕生すると考えています。
設計図の完成目標は 2027年初頭ですが、本当はそれより早く世に出したい。AGI が姿を現すその瞬間に、この仲立ちがすでに動いている方が安全だからです。しかし現状では資金も人手も足りず、前倒しは簡単ではありません。進捗を加速させるには新しい支援者を呼び込む情報発信が欠かせません。SNS でのシェアやゼミでの紹介など、あなたの一言が研究を大きく前に進めます。またNeuroQuadフレームワークの設計にかかわる議論もいつでもお待ちしていますので、いつでも気づきやアイデアをぜひ聞かせてください。
未来の知能を共につくりましょう。ご参加とご支援をお待ちしています。
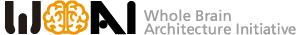
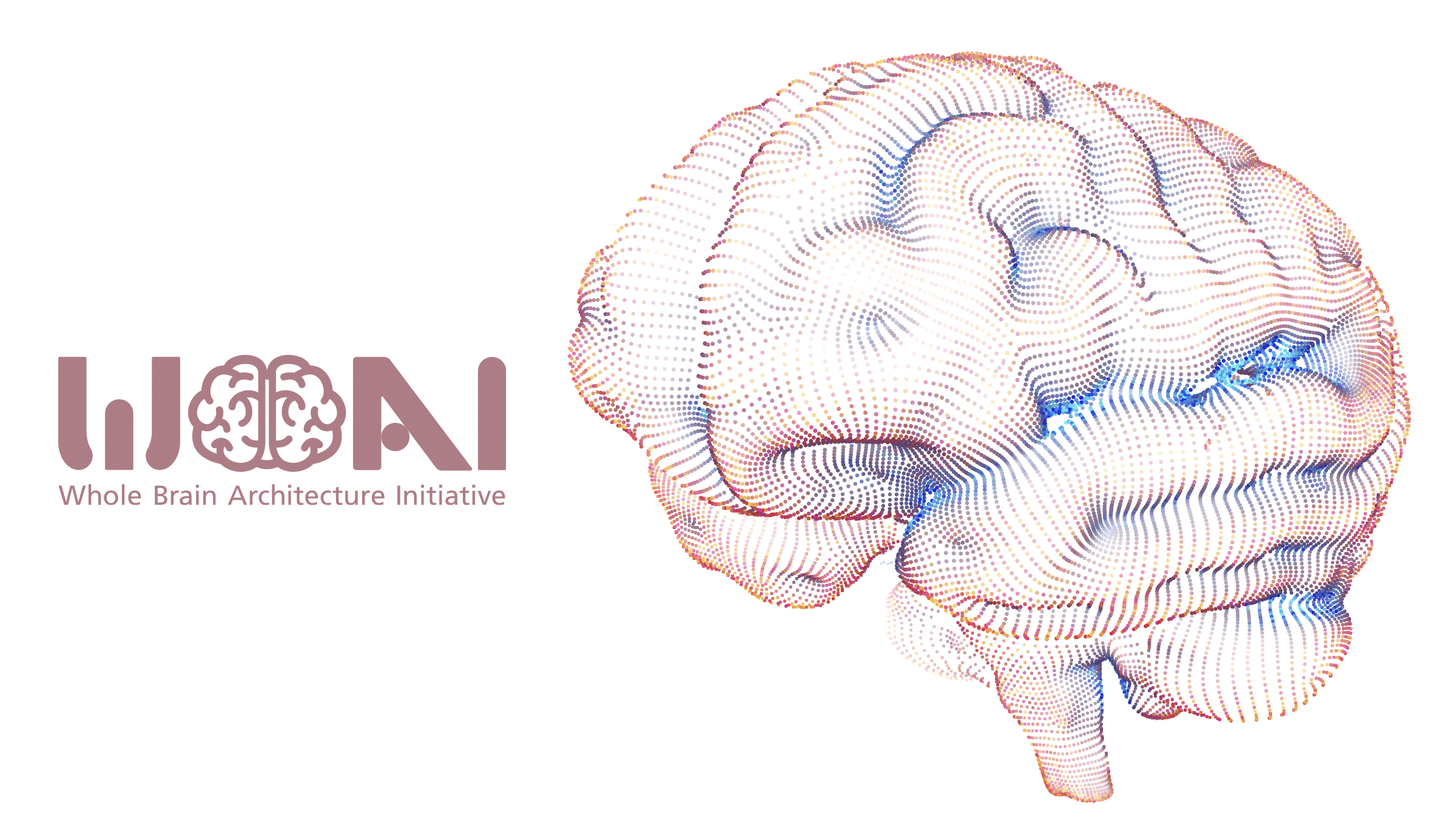


 English
English